�{�����e�B�A��Ï]���҂ɂ���ЎҌ������[����Ñ��k
2011.06.02
��a�l�b�g���y���z
�{�����e�B�A�̈�t���t�Ȃǂ��u�{�����e�B�A��Ï]���҂ɂ���ЎҌ������[����Ñ��k�v���J�݂��Ă��܂��B
�Q�n����������ÃZ���^�[�_�o���ȁ@�Ō��������Ȃǂ̃O���[�v�́A��ЎҌ������[����Ñ��k�������J�݂��܂����B
�A�h���X��info@311er.jp�ł��B
�����p���������B
���ڂ����̓t�@�C�����_�E�����[�h���Ă������������B
�@�@�@�@�@�@�m�o�n��a�̂��ǂ��x���S���l�b�g���[�N
�{�����e�B�A�̈�t���t�Ȃǂ��u�{�����e�B�A��Ï]���҂ɂ���ЎҌ������[����Ñ��k�v���J�݂��Ă��܂��B
�Q�n����������ÃZ���^�[�_�o���ȁ@�Ō��������Ȃǂ̃O���[�v�́A��ЎҌ������[����Ñ��k�������J�݂��܂����B
�A�h���X��info@311er.jp�ł��B
�����p���������B
���ڂ����̓t�@�C�����_�E�����[�h���Ă������������B
�@�@�@�@�@�@�m�o�n��a�̂��ǂ��x���S���l�b�g���[�N
�É��x������̂��ē�
2011.05.30
���@���F�����Q�R�N�U���P�X���i���j
�@�@�@�P�O:�O�O�i��t�j�`�P�T:�R�O
��@���F�É���w����w���������ʎx���w�Z
�@�@�@�@�䂤�䂤�فi�É��s������j
�����N�A��N�Ɓ@�����搶�A���J��搶��
�y�A�g�����s���܂����̂ŁA���N�͋v���Ԃ�
�ɍ��e��S�ōs���܂��B
�F�l�ɂ������̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�É��x�����@�ؑ�
�@�@�@�P�O:�O�O�i��t�j�`�P�T:�R�O
��@���F�É���w����w���������ʎx���w�Z
�@�@�@�@�䂤�䂤�فi�É��s������j
�����N�A��N�Ɓ@�����搶�A���J��搶��
�y�A�g�����s���܂����̂ŁA���N�͋v���Ԃ�
�ɍ��e��S�ōs���܂��B
�F�l�ɂ������̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�É��x�����@�ؑ�
�������˓��x���u�L�b�Y�̉�v���s���܂�
2011.05.29
�ȉ��̓����ŃL�b�Y�e�q�̏W����s���܂��B
���@���F�V���R���i���j�ߑO�P�O�����ߌ�S��
��@���F�L���s��t������
������͏��w�Z���w���Ђ����Ă̑̌��k���\��\�肵�Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�x�����@�e�r
���@���F�V���R���i���j�ߑO�P�O�����ߌ�S��
��@���F�L���s��t������
������͏��w�Z���w���Ђ����Ă̑̌��k���\��\�肵�Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�x�����@�e�r
�����x������̂��m�点
2011.05.24
�����x����������L�̓����ōs���܂��B
���@���F�����Q�R�N�U���Q�U���i���j�@�P�R�F�O�O�`�P�V�F�O�O�@�@
��@���F���n������u�斯�Z���^�[�@�UF�a��
����͐�y���ꂳ��̎q��Čo���k�A�܂��Љ�ɏo�Ċ��Ă��邲�{�l����ߋ��ɂ��Ă��b�����f�����܂��B
�F����̂��Q�������҂����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����x�����@��c
���@���F�����Q�R�N�U���Q�U���i���j�@�P�R�F�O�O�`�P�V�F�O�O�@�@
��@���F���n������u�斯�Z���^�[�@�UF�a��
����͐�y���ꂳ��̎q��Čo���k�A�܂��Љ�ɏo�Ċ��Ă��邲�{�l����ߋ��ɂ��Ă��b�����f�����܂��B
�F����̂��Q�������҂����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����x�����@��c
����k�֓��x������ƌ𗬉���J�Â��܂�
2011.05.21
���@���F�U���Q�T���i�y�j�P�R�F�O�O�`�P�V�F�O�O
��@���F�Ƃ����j�������Q��Z���^�[�@�p���e�B�i�F�s�{�s�j
�@�@�@ http://www.parti.jp/
�x������Ƃ��Ă͑���ڂ̊J�ÂƂȂ�܂��B
�����l�ł������̉������̎Q�������҂����Ă���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�����@��
��@���F�Ƃ����j�������Q��Z���^�[�@�p���e�B�i�F�s�{�s�j
�@�@�@ http://www.parti.jp/
�x������Ƃ��Ă͑���ڂ̊J�ÂƂȂ�܂��B
�����l�ł������̉������̎Q�������҂����Ă���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�����@��
�uPWS�t�H�[�����@in �V���v���J�Â���܂�
2011.05.20
�t�@�C�U�[��Ẫt�H�[���������L�̓����ŊJ�Â���܂��B
���@���F�V���X���i�y�j�P�S�F�O�O�`�P�U�F�O�O�i�P�R�F�R�O��t�J�n�j
��@���F�@�V�����j�]���v���U�TF�@�����C���i�a���̗p�ӂ���j
�v���O����
�P�S�F�O�O�`
�i��F�V�����͂܂��ݗÈ�Z���^�[�@�Z���^�[���@�����@�b�搶
����F�u�v���_�[�E�E�B���[�nj�Q�@�`�ŋ߂̘b��i����j�v
���ҁF�Ջ���ȑ�w�z�J�a�@�����ȋ����@�i��q�Y�搶
�Q������]�������́A�V���T���i�j�܂ł�
info@pwstakenoko.org
�܂Ő\�����ݐ�����₢���킹���������B
���@���F�V���X���i�y�j�P�S�F�O�O�`�P�U�F�O�O�i�P�R�F�R�O��t�J�n�j
��@���F�@�V�����j�]���v���U�TF�@�����C���i�a���̗p�ӂ���j
�v���O����
�P�S�F�O�O�`
�i��F�V�����͂܂��ݗÈ�Z���^�[�@�Z���^�[���@�����@�b�搶
����F�u�v���_�[�E�E�B���[�nj�Q�@�`�ŋ߂̘b��i����j�v
���ҁF�Ջ���ȑ�w�z�J�a�@�����ȋ����@�i��q�Y�搶
�Q������]�������́A�V���T���i�j�܂ł�
info@pwstakenoko.org
�܂Ő\�����ݐ�����₢���킹���������B
�V���x���𗬉�̂��m�点
2011.05.20
�ȉ��̓����Ō𗬉���s���܂��̂ň�l�ł������̕��̂��Q�����҂����Ă��܂��B
���@���F�T���Q�Q���i���j�ߌ�P���`
��@���F�T�c�ӂꂠ���v���U�QF�@
�@�@�@�@�@�@�@�V���x�����@�R��
���@���F�T���Q�Q���i���j�ߌ�P���`
��@���F�T�c�ӂꂠ���v���U�QF�@
�@�@�@�@�@�@�@�V���x�����@�R��
�V���|�W�E���̂��m�点
2011.05.11
��a�l�b�g���A���ٌ�m��u��Â���q�ǂ��̌����v���e�[�}�ŃV���|�W�E�����J�Â���Ƃ̂��m�点�����������܂����B
���ꖳ���E���O�\�����ݕs�v�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�e���ł��Q�����������B
���@���F�T���Q�P���i�y�j�P�R�F�O�O��t�J�n
��@���F���ٌ�m��قQ�K�z�[��
�ڍׂ̓`���V��������������
���ꖳ���E���O�\�����ݕs�v�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�e���ł��Q�����������B
���@���F�T���Q�P���i�y�j�P�R�F�O�O��t�J�n
��@���F���ٌ�m��قQ�K�z�[��
�ڍׂ̓`���V��������������
�U���S�����É��ł̍u����̉��肪���܂�܂���
2011.05.02
��ɂ��m�点�����悤�ɁA�U���S���i�y�j�ɖ��É��u���ۃz�[���v�ŊJ�Â���܂��u����i�t�@�C�U�[��Áj�̉��肪�{���܂�ƂȂ�܂����B
�i��搶�F�u�v���_�[�E�E�B���[�nj�Q�@�ŐV�̘b��v
���搶�F�u���^�ǂɂ��āv
�Ȃ��A���^�ɂ��Ă̎��₪����A���O�Ɏt���܂��B
���Ƃɂ��������������Ƃ������
info@pwstakenoko.org
�܂Ń��[���Ŏ�����e�������肭�������B
���ׂĂɉ��������邩�͂��ł��܂��A�̂��������̂ɂ��Ă͕ԐM�������Ă��������܂��B
�S���@�����C�x��
�i��搶�F�u�v���_�[�E�E�B���[�nj�Q�@�ŐV�̘b��v
���搶�F�u���^�ǂɂ��āv
�Ȃ��A���^�ɂ��Ă̎��₪����A���O�Ɏt���܂��B
���Ƃɂ��������������Ƃ������
info@pwstakenoko.org
�܂Ń��[���Ŏ�����e�������肭�������B
���ׂĂɉ��������邩�͂��ł��܂��A�̂��������̂ɂ��Ă͕ԐM�������Ă��������܂��B
�S���@�����C�x��
��10��k���x���̑���ƌ𗬉���J�Â��܂�
2011.05.01
�����F�@�����Q�R�N�U���P�Q���i���j�@�P�O���R�O���`�P�U��
�ꏊ�F�@�ΐ쌧�ΐ�S��X�s��
�@�@�@�@��X�s��������@���𗬊فu�J�����A�v
�@�@�@
�ΐ쌧���R�s�ɂ���u�ӂꂠ�������فv�̌��w��
��N����|�̎q�̉�ɂ����͂��������鎖�ɂȂ�܂��������ȑ�w�a�@�����Ȃ̈ɓ����f�搶�����������Ă̕����\�肵�Ă��܂��B�@
�ꏊ�F�@�ΐ쌧�ΐ�S��X�s��
�@�@�@�@��X�s��������@���𗬊فu�J�����A�v
�@�@�@
�ΐ쌧���R�s�ɂ���u�ӂꂠ�������فv�̌��w��
��N����|�̎q�̉�ɂ����͂��������鎖�ɂȂ�܂��������ȑ�w�a�@�����Ȃ̈ɓ����f�搶�����������Ă̕����\�肵�Ă��܂��B�@
�{�̏Љ�
2011.04.22
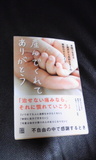
���̓x�w�Y��ł���Ă��肪�Ƃ��x�Ƃ����{����������܂����B
��a�l�b�g�i��a���ǂ��x���S���l�b�g���[�N�j����˗�������x������̒ÉY����Ɏ�ނ������Ă��������܂����B
������@��ɁuPWS�̍s���̖��ȂǁA����������̎����ɂȂ��Ă����v�Ƃ����v�������߂��Ă��܂��B
PWS�����łȂ��A���낢��Ȃ��q����̎����Љ��Ă��܂��̂ŁA�������������Q�l�ɂ��Ă���������K���ł��B
�w�Y��ł���Ă��肪�Ƃ��x
�Q�O�P�P�N�S���V�����s
�ďC�@�F��NPO�@�l�@��a���ǂ��x���S���l�b�g���[�N
���s���@������Ё@�o�ϊE
�艿�@�P�Q�O�O�~�{��
��a�l�b�g�i��a���ǂ��x���S���l�b�g���[�N�j����˗�������x������̒ÉY����Ɏ�ނ������Ă��������܂����B
������@��ɁuPWS�̍s���̖��ȂǁA����������̎����ɂȂ��Ă����v�Ƃ����v�������߂��Ă��܂��B
PWS�����łȂ��A���낢��Ȃ��q����̎����Љ��Ă��܂��̂ŁA�������������Q�l�ɂ��Ă���������K���ł��B
�w�Y��ł���Ă��肪�Ƃ��x
�Q�O�P�P�N�S���V�����s
�ďC�@�F��NPO�@�l�@��a���ǂ��x���S���l�b�g���[�N
���s���@������Ё@�o�ϊE
�艿�@�P�Q�O�O�~�{��
�|�̎q�̉�̒��Ԃ̊������j���[�X
2011.04.20

�É��x������ŕl���s�̉��{�ԐD�i����j���@�É��������A����Â̏������ߓW�ɂ����ē��I����܂���܂����B
�܂��A�S�����ʎx���w�Z�����Ղ̏�������ł��D�G�܂���܂���܂����B
�ʐ^��Y�t���܂����A���L�T�C�g�i�C���^�[�l�b�g�M�������[�j�ł������ɂȂ�܂��B
���ЁA���q�����ɂ������Ă����Ă��������B
�@
http://www.nise.go.jp/kenshuka/jokan/gallery/kobetu/17s31.html
�܂��A�S�����ʎx���w�Z�����Ղ̏�������ł��D�G�܂���܂���܂����B
�ʐ^��Y�t���܂����A���L�T�C�g�i�C���^�[�l�b�g�M�������[�j�ł������ɂȂ�܂��B
���ЁA���q�����ɂ������Ă����Ă��������B
�@
http://www.nise.go.jp/kenshuka/jokan/gallery/kobetu/17s31.html
�����Q�R�N�x�����C�x������ƍu����̂��m�点
2011.04.16
�����F�@�����Q�R�N�U���S���i�y�j
�@�@�@�@�ߌ�P���`�Q���R�O���i��t�P�Q���R�O�����j
�ꏊ�F�@���ۃz�[���i���ڂ��z�[���j�T�O�P�����i���É��w���Q���j�@
�Ȃ��A�x������I����A�����Łu�Ȃ��₩���ǂ��N���j�b�N�v�̏㞊�搶�ɂ��|�̎q�̉���C��������ɍu����i�t�@�C�U�[��Áj����悵�Ă��������܂����B
����́A����̊S�̋����u���^�v�ɂ��āA���搶�̂��u���Ɖi��搶�ɂ��o�v�r�̂��u���Ƃ����M�d�ȋ@��ƂȂ�܂����B
����J�荇�킹�Ă��Q�����������B�i�ڍׂ͈ȉ����������������j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����C�x���̕��͎Q���\���A�ϔC����T���Q�O���܂łɖF��܂ł��肢���܂��B
�����C�ȊO�̎x���̕��ōu����ɎQ������]��������info@pwstakenoko.org�܂��͊e�x�����܂ł��A���������B
�l���̓s���ʼn������Ƃ����Ă��������܂��B
������������������������������������������������������������
�u����́F�v���_�E�B���[�nj�Q�u����
�����F�����Q�R�N�U���S���i�y�j
�ꏊ�F���ۃz�[���i���ڂ��z�[���j
���S�T�O�|�O�O�O�Q���É��s�����於�w�R�|�P�T�|�X�@TEL�F�O�T�Q�|�T�U�P�|�X�W�R�P
���F�T�O�P�����i�u�����j�E�S�O�U�����i�u�t�T���j�E�V�O�Q�����i�t���[�X�y�[�X�j
�����F�Ȃ��₩���ǂ��N���j�b�N�@�@���@�㞊�@���i�搶�@
�����ʍu���P
�P�T�F�O�O�`�P�U�F�R�O�i���^�������܂ށj
�u�v���_�E�B���[�nj�Q�@�ŐV�̘b��v�i����j
�Ջ���ȑ�w�z�J�a�@������
�����@�i��@�q�Y�搶
�����ʍu���Q
�P�U�F�S�T�`�P�V�F�S�T�i���^�������܂ށj
�u�����ǂɂ��āv�i����j
���ƌ��������ϑg���A����@����a�@���`�O��/�ҒŐҐ��Z���^�[
�����@���@�I���搶
�@�@�@�@�ߌ�P���`�Q���R�O���i��t�P�Q���R�O�����j
�ꏊ�F�@���ۃz�[���i���ڂ��z�[���j�T�O�P�����i���É��w���Q���j�@
�Ȃ��A�x������I����A�����Łu�Ȃ��₩���ǂ��N���j�b�N�v�̏㞊�搶�ɂ��|�̎q�̉���C��������ɍu����i�t�@�C�U�[��Áj����悵�Ă��������܂����B
����́A����̊S�̋����u���^�v�ɂ��āA���搶�̂��u���Ɖi��搶�ɂ��o�v�r�̂��u���Ƃ����M�d�ȋ@��ƂȂ�܂����B
����J�荇�킹�Ă��Q�����������B�i�ڍׂ͈ȉ����������������j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����C�x���̕��͎Q���\���A�ϔC����T���Q�O���܂łɖF��܂ł��肢���܂��B
�����C�ȊO�̎x���̕��ōu����ɎQ������]��������info@pwstakenoko.org�܂��͊e�x�����܂ł��A���������B
�l���̓s���ʼn������Ƃ����Ă��������܂��B
������������������������������������������������������������
�u����́F�v���_�E�B���[�nj�Q�u����
�����F�����Q�R�N�U���S���i�y�j
�ꏊ�F���ۃz�[���i���ڂ��z�[���j
���S�T�O�|�O�O�O�Q���É��s�����於�w�R�|�P�T�|�X�@TEL�F�O�T�Q�|�T�U�P�|�X�W�R�P
���F�T�O�P�����i�u�����j�E�S�O�U�����i�u�t�T���j�E�V�O�Q�����i�t���[�X�y�[�X�j
�����F�Ȃ��₩���ǂ��N���j�b�N�@�@���@�㞊�@���i�搶�@
�����ʍu���P
�P�T�F�O�O�`�P�U�F�R�O�i���^�������܂ށj
�u�v���_�E�B���[�nj�Q�@�ŐV�̘b��v�i����j
�Ջ���ȑ�w�z�J�a�@������
�����@�i��@�q�Y�搶
�����ʍu���Q
�P�U�F�S�T�`�P�V�F�S�T�i���^�������܂ށj
�u�����ǂɂ��āv�i����j
���ƌ��������ϑg���A����@����a�@���`�O��/�ҒŐҐ��Z���^�[
�����@���@�I���搶
�u���ː����k�v�̂��m�点
2011.04.04
��a�l�b�g���ȉ��̂悤�ɂ��m�炪����܂����B
�D�P������c���̂����e��ΏۂƂ������ː��̉e���Ɋւ���d�b���k�J�݂̂��m�点
������ꌴ�����̂ɂƂ��Ȃ����ː��̉e���ɂ��āA���܂��܂ȏ��≯��������Ă���A�����̐l�X���s���̓��X���߂����Ă��܂��B��a�̂��ǂ��x���S���l�b�g���[�N�ł́A�����q�͈��S����������ψ��̍��ؗǘa�搶�i����Õ�����w�q�������j�ɂ��A�D�P�����邢�͓��c���̂����e��ΏۂƂ������ː��̉e���Ɋւ����t�ɂ����Ԍ���̓d�b���k���J�݂��܂��B�ǂ��������p�������B
�m���k���n�@���T���j���@�ߌ�Q���`�ߌ�T��
�m�d�@�b�n�@�O�R�|�T�W�S�O�|�T�X�V�R
�m���k���n�@����
�m���@�ԁn�@�S���P�R���i���j����U���Q�X���i���j�܂ł̖��T���j���B
�@�@�@�@�@�@���U���W���i���j�݂̂U���X���i�j�ƂȂ�܂��B
�m���k���n�@���ؗǘa�i����Õ�����w�q�������E���_�ސ쌧�����ǂ���ÃZ���^�[�����j
�D�P������c���̂����e��ΏۂƂ������ː��̉e���Ɋւ���d�b���k�J�݂̂��m�点
������ꌴ�����̂ɂƂ��Ȃ����ː��̉e���ɂ��āA���܂��܂ȏ��≯��������Ă���A�����̐l�X���s���̓��X���߂����Ă��܂��B��a�̂��ǂ��x���S���l�b�g���[�N�ł́A�����q�͈��S����������ψ��̍��ؗǘa�搶�i����Õ�����w�q�������j�ɂ��A�D�P�����邢�͓��c���̂����e��ΏۂƂ������ː��̉e���Ɋւ����t�ɂ����Ԍ���̓d�b���k���J�݂��܂��B�ǂ��������p�������B
�m���k���n�@���T���j���@�ߌ�Q���`�ߌ�T��
�m�d�@�b�n�@�O�R�|�T�W�S�O�|�T�X�V�R
�m���k���n�@����
�m���@�ԁn�@�S���P�R���i���j����U���Q�X���i���j�܂ł̖��T���j���B
�@�@�@�@�@�@���U���W���i���j�݂̂U���X���i�j�ƂȂ�܂��B
�m���k���n�@���ؗǘa�i����Õ�����w�q�������E���_�ސ쌧�����ǂ���ÃZ���^�[�����j
�i�o�`�k�Џ��i��14��)
2011.03.26
���i�o�`�k�Џ��i��14��j--------------------------2011.3.25-*
�@�����A�����ǂɂP�{�̔ߒɂȓd�b������܂����B
�@�u�������܃A���[�i�ɔ��Ă��Ă��镟������̐l�����̂Ȃ��ɁA
���͂̊��҂��������邪�A���͂������Ë@�ւ̊m�ۂ��Ԃɍ�����
���Ȃ��B���҂���́A�ѕz�P���ł��낪����Ă���ŁA�ƂĂ���
�������B�����s���̃z�e���Ȃǂ����Ɗ��̂����Ƃ���Ɉڂ낤�Ǝv��
�Ă��A�ړ������i���Ȃ��B�����葁���̂̓^�N�V�[�����A�^�N�V�[
��̕��S�͑�ρB���߂Ĕ��҂̈ڑ����Ë@�ււ̒ʉ@��p�́A����
�ȂƂ������犳�ҕ��S���Ȃ��悤�ȑ[�u���Ƃ��Ă��炦��悤�A���ɗv
�����Ăق����v�ƁB
�@�������ʂ̐t�F��A�S�t���Ȃǂ����҂̈ڑ��ɂ��Ă͍��⎩����
�Ƃ̘A�g�̂��Ɩz�����Ă��Ă��܂����A�ڑ��̂��߂̌�ʔ�ɂ��ẮA
�����L���Ȏ��łĂĂ��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B�����J���Ȏ��a��ۂɕ�
���ƁA���s�̍ЊQ�~���@�ɂ���Ў҂����Ă�����̂��鎩��
�̂̔��f�ŏo�����Ƃ͂ł���Ƃ̂��Ƃł��B�������A���ꂾ���̍ЊQ��
�Ȃ�A������A���ɂ������`�k�r��l�H���͊��҂͍ŗD��ł�
�Ή����K�v�ł����A���ɂ������������a���ҁA���x�̍ЊQ�ŏ��Q��
�����芴���ǂȂǂň�Ë@�ւłً̋}�Ή���A����Ԃ����P�ł����
��Ɉڂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��P�[�X�͂�������o�Ă��邱�Ƃ͖ڂɌ�����
���܂��B
�@�����̂ł̔��f�����ł͌��E������܂��B���{�͋߂����ʗ��@������
���Ƃ̂��Ƃł����A���̂Ȃ��ł͂��Ђ����������������Ƃ��đΉ���
����悤�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł��B��Q�҂��a�A�����������҂ւ̑Ή�
�́A�������ē��ʂȂ��̂ł͂Ȃ���Ў҂��ׂĂ̐l�����̖��ł���A
�Ђ��Ă͔�Вn�ȊO�̍����S�̖̂��ł��B
�@�������͐k�БO����A��a���A���������̖�肪�A�����̓��ʂȐl
�����̖��ł͂Ȃ��A�N�������W���邩�킩��Ȃ����Ƃ��ĂƂ�
���邱�ƁA��a��A��Q�ґ���g�[���邱�Ƃ��A���{�̕����A���
�̐������グ���邱�Ƃł���A�������̊��҉^���A��Q�҉^���͂���
�����Љ�I�ȈӋ`�̂���^���ł���Ǝ咣���Ă��܂������A���̂��Ƃ�
���̐k�Б�̂Ȃ��ł���������ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���܂��B�i���J�j
���ȉ��A�X�ݏZ�̋v�ۓc��������̃��[�����Љ�܂��B�v�ۓc����
�͑S���S���a�̎q�ǂ���������ŁA�X���x���������Ă��܂��B
----------------
����A�X���̐�V���S��������ɁA��������Ў҂��ی�������
���A�Љ��E�J���e�����A�����i�q�ǂ��j�����p���Ă������Ȃ�
��ԂŎ�f�ł��邩�₢���킹���Ƃ���A���������̈�t�Ԃ̃l�b�g��
�[�N�ŁA�X�s�A�O�O�s�A���ˎs�Ōv�T�a�@������Ă�����͂�
������Ă���܂����B���ɁA�O�O�̈�t�͍O�O�ɔ��Ă����q�ǂ���
�S�������ɔC����ƌ����Ă���܂����B���J�Ȃ̒ʒB��ǂފԂ��Ȃ���
�t�B���Ǝ��œ����Ă���Ă��܂��B�i�ی��̌��͂R��11���Ɍ��J�Ȃ�
�ʒB���o�Ă��܂�������̈�t�͓ǂ�ł��鎞�Ԃ�����܂���j
���A���҂̂��߂̔�������A�����̂������Œ�������̐���
��������܂��B�܊p�������������~�����߂ɂ́A���n�ł̎��Ԕc��
�ƂƂ��ɑ���Ƃ�悤�A���{�ɋ����i�������ł��B���{�̓����͌��
���ɂȂ��Ă��܂��B���̏Z�ގO�����Вn�ł��B�Ôg�ʼn�œI�Ȕ�Q
�����n��A�`�ɂ̓{�����e�B�A�ƂƂ��ɕČR���{�����e�B�A�Ƃ���
��������ϋɓI�ɕ����Ɍ������x���������s���Ă��܂��B�i�l���A�����A
�d�@�A�R���j�B�ʂ����Đ��{�͔�Вn�Ɏ�����荞��ł���̂��H�^��
�Ɋ����Ă��܂��B
���T���j���ɎЗp�œ����֍s���܂����B�H�c��`�͔��Â��A�����Đl��
���Ȃ��d�Ԃ��l���܂�ŁA�ǂ��ɍs���Ă����̔߂������o���܂����B
���n�̕����ƂƂ��ɁA���{�̌o�ς����C�����߂���悤�A�܂��͓���
�����C�ɂȂ�Ȃ���Ɗ����܂����B
������A����A�����ŊJ�Â��Ċ��C�t���܂��傤�B
���i�o�`�́A�S���Q���`�R���̂Q���ԁA�����s���ŗ�������J�ÁB�܂�
�����_�ł́A�����\��ǂ���A�T���Q�X���i���j�ɑ�V��A���R�O
���i���j�ɍ����s�����s�����ƂƂ��A����O���̂Q�W���i�y�j�ɁA
��P�P������A������������ŊJ�Â��邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�y���R�אl�搶�i�S����a�Z���^�[�������j����̃��b�Z�[�W�Љ�z
���쌴����\���A�S����a�Z���^�[�������ŁA�������_�E�_�o�Z
���^�[�a�@���̎��R�搶����A���̂悤�ȃ��[��������܂����Ƃ̘A��
������܂����̂ŏЉ�܂��B
----- Original Message -----
�쌴�����l
��k�Ђƌ������̎��ɍ���ɊF���ʂ��Ă��܂��B
��a���҂���ւ̎x���A�l�X�s���Ă��܂����A�ł��[���ŋꂵ���Ή�
�Ɋ撣���Ă����́A���k��w�̐ؐ��u�搶�B�̊����Ɍ����܂��B
�{��̍���搶���̐l�H�ċz�ɂȂ��ꂽ���҂���B�̋~���ɓ��{�_�o
�w��⍑���a�@�@�\�̕a�@��搶������{�݂�h����Ðl�̃��X�g
���쐬���ē�a��Âɋ��͂��Ă��܂��B
��̋����Ɋւ��Ă͊e�w��������Ă�������܂��B
���R�אl�@�Ɨ��s���@�l�@�������_�E�_�o��Ì����Z���^�[�a�@��
�y�L������z
����ЎҎx�����J�ȁA�����N���ی����Ə�������
�i���{�o�ϐV��2011�N3��25���t�����j
�@�����J���Ȃ͓����{��k�ЂŔ�Ђ������Ǝ҂ƌٗp�҂ɂ��āA
�����N���ی�����Ə����錟���ɓ������B
�@�Ə��ɂ͖@�����ɂ������݂���K�v������B���Ȃ͐��{�S��
�Ŕ�ЎҎx���@���Ƃ�܂Ƃ߂鎞�ɁA����@�荞�ޕ��j�B�n�k
�Ŕ�Q�����l���Ƃ��x������̂��_�����B
�@���c�Ǝ҂�p�[�g�J���҂��������鍑���N���ł́A���łɔ�Ў�
�̕ی�����Ə����Ă���B����A��Ђœ����l����������N���͍�
�Q�ɂ��Ə����x��݂��Ă��Ȃ��B
�@�����P�X�X�T�N�̍�_��k�Ђ͔�Q���傫���������߁A��ЎҌ�
���ɕی����̖Ə����x��݂����B���J�Ȃ͓����{��k�Ђ��X�T�N��
��Q����Ɣ��f�A�Ăѓ����݂���K�v������Ƃ݂Ă���B
�@����̑Ώۂɂ͊��A�{��A�������ȂǂōЊQ�~���@���K�p����
���n���z��B�Ζ��悪��Ђ��Ď��Ƃ����藧�����A�x�����鋋�^
����������������ł����ƂƂ��̏]�ƈ����Ə��̑ΏۂɂȂ�B
�@�܂��A��_��k�Ђ̎��̓���ł́A�N���ی����̖Ə����Ԃ͕ی�
�����x���������̂Ƃ݂Ȃ��Ă����B��������l�̈����ɂ��邩�͍�
��l�߂�B
�@���łɌ��J�Ȃ͔�Вn�ɑ��A�����N���ی����̔[�t�������n��
�Ă���B�����N���Ƌ����ۂ̌��N�ی��ɂ��āA��Ђ�������
���̏ꍇ�A�ЊQ�ɂ�鍬�����I����Ă���ی����̔[�t�����߂�B
�@�ΏۂƂȂ�n��͐X�A���A�{��A�����A���̂T���B�Ώێ�
�Ǝ҂͂P�P���ɂȂ錩���݂��B�a����������̈������Ƃ������~��
���B
�@���c�Ǝ҂�p�[�g�œ����l�����鍑���N���ł́A�\���葱������
��Εی����i���P���T�P�O�O�~�j�̎x������Ə�����B�Z���ƍ�
�Ȃǂ������ނ˂Q���̂P�ȏ㎸�����l���ΏۂŁA�V�����܂łɑS��
�̔N���������Ŏ葱������K�v������B
-----------------------------------------------------------
����a���҂�f�@�A�w��a�@�ȊO���|��d�Ō��J�Ȓʒm
�i�����V��2011�N3��25���t�����j
�@�����J���Ȃ͂Q�S���A�����d�͂Ⓦ�k�d�͂ɂ��v���d������A
��a��l�H���͂̊��҂炪���ȕ��S����������Ă���w��̈�Ë@
�ւ���f�ł��Ȃ��ꍇ�����邱�Ƃ���A�ʂ̕a�@�ł���f�ł����
���ɂ���[�u��s���{���ɒʒm�����B
�@���J�Ȃɂ��ƁA���⎩���̂���Ô���������Ă����a���҂�
��U�W���l�B�ʏ�́u���莾����Îҏv���g���A�����ɋL��
���w���Ë@�ւŎ��Â��邪�A�v���d�ɂ��w���Ë@�ւ�
�@�\���Ȃ��ꍇ���N���蓾�邽�߁A�Љ��ȂǕʂ̕a�@�ł���f��
����悤�ɂ���B
�@�܂��A�l�H���͊��Җ�R�O���l�͏�Q�Ҏ蒠���擾���Ă���P�[
�X���������A�u�����x����Îҏv�ɋL�����w��̈�Ë@�ֈȊO
�ł���f�ł���悤�ɂ���B�y��q�b�z
���ʒm�́A�����J���ȃz�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j8f-img/2r985200000165ko.pdf
------------------------------------------------------------
���t�@�C�U�[�@�����̃I�����C���Ǘᑊ�k���J�n
�@���e��GIST
�@�i�~�N�XOnline�@2011/03/24 05:02�j
http://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/40500/Default.aspx
�@�t�@�C�U�[�͂Q��������A�����Ɋւ��Ĉ�t����I�����C��
�ŏǗᑊ�k���t������g�݂��n�߂��B
�@���Ђ̈�Ï]���Ҍ�������������E�F�u�T�C�g�uPfizerPRO�v��
�V�R���e���c�Ƃ��āuPfizerPRO CaseStudy�v���J�݁B���e�Ƃ�
�Ċ����GIST�i�����NJԎ���ᇁj��Ώۂɂ����uGIST�Ǘᑊ
�k���v�̃T�[�r�X���n�߂��B
�@�ʏǗ�̑��k����オ�A���ɗՏ��I�ɎQ�l�ɂȂ�Ǘ�
�ɂ��Ă̓f�[�^�x�[�X�o�^��PfizerPRO����ɑ��Č��J����B
�@���Ђ͂��̃r�W�l�X���f���ɂ��ē����o�肵�Ă���B
�@���Ђ͍���̐V�R���e���c�ɂ��āA�u�����ɑ��ēK��
�Ǘᑊ�k���ł���d�g�݂ƁA�X�Ƀf�[�^�x�[�X�����邱�ƂŁA��
���̈�ÊW�҂ŏ��̋��L�Ǝ��Â̍œK����}�邱�Ƃ�ړI��
���Ă���v�Ɛ������Ă���B
�@GIST�͔��ǐ���10���l������Q�l�Ɣ��Ɋ�Ȃ���B���Â̑I
�����͎�Ɏ�p�ŁA�Ö@�̓C�}�j�`�u�A�X�j�`�j�u�̂Q�܂Ɍ�
����B�����GIST�Ǘᑊ�k���͕a���A���ː��A���ȁA�O�Ȃ̊e
�����GIST���Â̐��Ƃ̋��͂Ă���A�b�s��w���摜�t�@
�C���Ȃǂ��܂߂ăI�����C���ŏǗᑊ�k�ł���B���k�@�\�͉����
�t����A���J�Ǘ�͉���S�����Q�Ɖ\�B
�@���Ђ́A��×p���i�̏��Ȃǂ��C���^�[�l�b�g������肷��
��Ï]���҂������Ă��邽�߁A�l�q�ɂ����ɂ��킹�ăl�b
�g�ł̏�����������K�v������Ɣ��f���APfizerPRO��10�N
�Q������J�n�����B
�@�ŋ߂ł�The New England Journal of Medicine�iNEJM�j�Ɍf��
����Ă���S�Ă̘_�����t���y�[�p�[�ʼn{���ł���悤�ɂ���ȂǁA
�R���e���c������������B
�y���Ғc�̂���̘A���E���z
���S���S���a�̎q�ǂ�������----------------------------------
�i�����ǒʐM�u�n�b�g�͂��Ɓv�Վ���2011�N3��24���t���j
�� ��Вn�̎x�����
����茧�x�����@����݂Ȃ����ł��I
�x�����̋e�r����̉�����A���b���܂����B
�����R�l�Ŏ蕪�����ĉ���̈��ۊm�F�̘A�������܂����B�C������
�Z��ł�������Ôg�̉e���Ŕ�Q���Ђǂ������ł����A���ۂ͊m�F��
���������ł��B�����ł��A�K�\�����Ɠ����A�H�i�A�����Ȃ���Ԃ��[
���ł��B�u�݂Ȃ���̐����ƂĂ��������v
������畷�����Ă����b�c
����������i��D�n�s�j�A����͖��������������X�͒Ôg�̉e���Ń_��
�ɂȂ��Ă��܂����B
����D�n�s�̒��w�P�N���̉���̕��́A���܂��ܕa�@�ɍs���Ă��Ċw
�Z���x��ł������A�����w�Z�̓������͍s�����킩��Ȃ���������B
�Ȃ��Ȃ��Ă��܂������a�@�܂ōs�����ɂ����B�Ȃ�Ƃ��ً}�ԗ�
�ɏ悹�Ă�����ĕa�@�ɍs�����Ƃ��ł����B���̌�͐e�ʂ̉Ƃɔ��
������B
���e�r����̂��q��������[�t�@����������ł��Ď��]�Ԃɏ��̂�
��߂�悤�Ɍ����Ă��āA�ӂ���w�Z�܂�30�������ĕ�����
�ʂ��Ă���B���x�������g�Q���Ƃ��Ă���g�̂ŁA�����̕��˔\
���S�z�����A����}��������ɂ��K�\�������Ȃ��Ăł��Ȃ��B
�������z���ÃZ���^�[�ɐS���a�̊��҂͏W�����Ă���B���
�ƕa�@�ɍs���Ă��Q�T�ԕ��������炦�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
���ݑ�_�f�̐l�A�_�f���c��킸���ɂȂ�q���q���������A�Ȃ�Ƃ�
��ЂɘA�����Ƃ�ď��������B
���w�Z�ɂ��Ēn�k�����āA�Z��ɃW�����p�[�����Ŕ������A�e��
�̘A�����Ȃ���Ȃ��Ăނ����ɂ��Ă��炦�Ȃ��āA���ׂ��Ђ��Ěb
�����Ђǂ��Ȃ��Ă��܂��̒�����邭�Ȃ����B
28���ɂ͖�������J���āA���ꂼ�ꕷ�����������̕��̏�����
�����\��ł��܂��B
���X���x����
��Вn����X���̈�Ë@�ւɂ�����ꍇ�ɂ��Ă̏��
�i�v�ۓc�x��������̃��[���Ɠd�b�j
�X���O����̔��҂ŐS���a���̐f�ÂȂǎ����Ή��ɂ��m�F��
�܂����B
�₢���킹������
�����A�{��A��肩��̔��҂����X�����Ɉړ����n�߂Ă��܂����A
�{���ɔ����S���a���E�҂̐f�@�A���Âɂ������Ď��̎������O��
�Ă���܂��B
�@ ���N�ی��������Ă��Ȃ��i���o�A�����ē������Ȃ������j
�A �Љ�Ȃ�
�B ��p���p���Ă������Ȃ��B
���̂悤�ȃP�[�X�ʼnʂ����Ď�f�ł���̂��H�@����Ă����a
�@�͂��邩�H
�����a�@�@�\�O�O�a�@�����H�搶�֊m�F���������ʁA���L�̈�Ë@��
�őΉ����Ă�������Ƃ̉����������܂����B
�E�X�s���X�s���a�@�i�����ȁE�s���搶�j
�E�O�O�s���O�O��w��w���t���a�@�i�����ȁE�����搶�j�A�����a�@
�@�@�\�O�O�a�@�i�����ȁE�����搶�j
�E���ˎs���X�J�Еa�@�i�����ȁ@����搶�j�A���ˎs���a�@
��t�A�a�@�Ԃ̌��ȂǍ����搶���S�ʓI�Ƀo�b�N����Ƃ������Ƃ�
�����B
�������J���ȁ@�ی��Lj�Éۂ�3/11�����A���u��ی��ҏؓ��̒�
�ɂ��āv�ɂ����āA�u�����A���N�����A��p�ҕی��̔�ی��҂ɂ�
���Ă͎��Ə����A�������N�ی��y�ь������҈�Ð��x�̔�ی��҂�
�����Ă͏Z����\�����Ă邱�Ƃɂ��A��f�ł���戵���Ƃ���̂�
���̎��{�y�ъW�҂ɑ�����m�ɂ��āA��R�Ȃ��������ꂽ���B�v
�Ƃ����w�����o�Ă��܂��B�������A���[�̈�Ë@�ւ܂ŁA���������A
�����͂����Ĕ�Вn�܂ōs���͂��Ă��Ȃ��悤�ŁA����́A���
�x�����n���̈�t�ɓ������������Đ搶�������Ă��������܂����B��
���A�A��B�ɂ��ẮA�����J���Ȃ���͉��̎w�����o�Ă��炸�A��
�������Ë@�֔C���ł��B�����J���Ȃ���́u�k�Б�v�Ƃ��Ă���
����̘A���������o���Ă��܂����A���ꂾ���ł͕s�\���ŁA����̂�
���ɒn���̈�t�̂��s�͂ɂ��Ή��ł��Ă���̂�����̂悤�ł��B
�i�{�������ǁj
���������x�����i�Ζ؎x�������獡�䗝�����d�b�ŕ������j
�i22���i�j��10:30���A�����x�����̖Ζ���d�b�Ŕ�Џ�
�Ȃǂ��܂����j
�����̉Ƃ͕����w�ɋ߂��A�w���瓹�H�ɑ傫�ȋT�����Ă��܂��B
�S�����ƕ��݂̂����A�����̂Ƃ���͈�ԉw���牓���̂ł����A
�߂��Ƃ���A�Ԏ��A���F�A���F�ƂȂ��Ă���A�䂪�Ƃ��S��͖Ƃ��
�������A�X���Ă���Ƃ��������A�����A�s���猚���̎g�p�Ɋւ���
�f�f���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B��������A���ɂ��܂������A
��͎���ɖ߂�܂����B���i�a���j�͎����̖��̂Ƃ���ɂЂƂ܂��A
�����Ă��܂����A�X�g���X�������Ă���悤�ŁA��������ɖ߂�
��ɂȂ�Ǝv���Ă��܂��B
��N�A�����ő�����J�Â��鎞�ɁA������@��ɑS���̉���݂̂Ȃ�
��ɁA����A�����̏ꏊ���o���Ă��炨���ˁA�Ƙb���Ă����̂ɁA��
�����A����Ȍ`�ŕ����̖��O���S���ɍL����Ƃ͎v���܂���ł����B
�n�k�����邱�ƂȂ���A���A�����ň�Ԗ��ɂȂ��Ă���̂́A����
�ł��B��������Ă��Ȃ��n��ɂ��A���R�����͏Z��ł���A���
�v�ƌ�����炵�Ă���̂ɁA���]�ɂ��A�������Ă��錻��
�߂����ł��B�������͖����A�����ŕ�炵�Ă��܂��A���ː��ʂ����
�ɂȂ�قǂł͂Ȃ��̂ɁA�������畨���̗A�����x���ǂ�قǂ̔��
�����Ƃ����̂ł��傤���B��ÂɑΉ����Ăق����ł��B
���͎���ɂ�����̂�H�ׂĐ������Ă��܂��B�ߏ��̉������ƐH��
����������āA�[�H�����ɂ��Ă��܂��B�������o�Ă���悤�ɂȂ�A
�����A�ق��Ƃ��邱�Ƃ�����܂��B
�������A�������b�Ƃ��āA
����Q�Ҍٗp�ō̗p����A�k�Г��ً̋}���ɂ͂��Ԃ��ē����Ă����
�͂��������̂ɁA�݂�Ȃ����肾���A�����������ē��������r���ő�
�͂��������A���铯���Ƃ͗���Ă��܂����B
�����ł́A���ׂ��͂��͂��߂Ă��āA�a���Ɋ���������̂���
�킭�ĕt���Y���Ă���Ɓu�ߕی�v���ƌ���ꂽ�B
���e���r�ł́A���Ȃ�������C�ɗV��ł���q�ǂ��A�ϋɓI�Ɏ�
�`�����Z���Ȃǂ��ʂ��o����Ă��邯��ǁA�����Ƃ��ē����Ȃ��q��
��������B���N�����Q�҂ɔz�����ƌĂт����Ă��Ă��A���̂Ȃ�
�ɂ͓�����Q�҂͊܂܂�Ă��Ȃ��B���������a�C�̎q�ǂ��̂��Ƃ͓�
�ɂȂ��B���Ԃɕa�C�̂��Ƃ��F�m����Ă��Ȃ��ȂƊ�����B
�������������҂��������Ƃ��炦�Ă��A���܂łP���������炦����
���A���̖�̔z�����u���ɂȂ邩�킩��Ȃ��v�ƂQ�T�ԕ���������
���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ̂ł����܂ň����Ȃ��l���A���炦�邤����
�Ɛf�@���A���������Ă��邱�Ƃ�����B�x���̐l�Ƙb��������
����Ȏ��ԂɂȂ�����A�a�C�̎q�������ĂȂ�Ă����Ȃ���ˁB�ߍ�
�ȏɑς���Ȃ���B���N�Ȑl�ł��h���̂ɁB
------------------------------------------------------------
���e���a�c�̂̎��g�݂�����A�i�o�`�����ǂɂ����肭�������B
*------------------------------------------------------------*
���ً}�ȏꍇ�̘A���͐��J�̌g�сi090-8501-4281�j�܂ł��肢���܂��B
�Ȃ��A���[���͐����`�F�b�N���Ă��܂��B
�i�o�`�z�[���y�[�W�@http://www.nanbyo.jp/
�k�Џ��u���O�y�[�W�@http://blog.goo.ne.jp/jpa2011
�i������ɐ��������������j
���{��a�E���a�c�̋��c����ǒ��@���J�K�i
���̂i�o�`�iJapan Patients Association�j
��162-0822�����s�V�h�扺�{�䒬2-28
�ѓc���n�C�^�E��610��
�d�b03-6280-7734�@�e�`�w03-6280-7735
http://www.nanbyo.jp/�@jpa@ia2.itkeeper.ne.jp
*------------------------------------------------------------*
�@�����A�����ǂɂP�{�̔ߒɂȓd�b������܂����B
�@�u�������܃A���[�i�ɔ��Ă��Ă��镟������̐l�����̂Ȃ��ɁA
���͂̊��҂��������邪�A���͂������Ë@�ւ̊m�ۂ��Ԃɍ�����
���Ȃ��B���҂���́A�ѕz�P���ł��낪����Ă���ŁA�ƂĂ���
�������B�����s���̃z�e���Ȃǂ����Ɗ��̂����Ƃ���Ɉڂ낤�Ǝv��
�Ă��A�ړ������i���Ȃ��B�����葁���̂̓^�N�V�[�����A�^�N�V�[
��̕��S�͑�ρB���߂Ĕ��҂̈ڑ����Ë@�ււ̒ʉ@��p�́A����
�ȂƂ������犳�ҕ��S���Ȃ��悤�ȑ[�u���Ƃ��Ă��炦��悤�A���ɗv
�����Ăق����v�ƁB
�@�������ʂ̐t�F��A�S�t���Ȃǂ����҂̈ڑ��ɂ��Ă͍��⎩����
�Ƃ̘A�g�̂��Ɩz�����Ă��Ă��܂����A�ڑ��̂��߂̌�ʔ�ɂ��ẮA
�����L���Ȏ��łĂĂ��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B�����J���Ȏ��a��ۂɕ�
���ƁA���s�̍ЊQ�~���@�ɂ���Ў҂����Ă�����̂��鎩��
�̂̔��f�ŏo�����Ƃ͂ł���Ƃ̂��Ƃł��B�������A���ꂾ���̍ЊQ��
�Ȃ�A������A���ɂ������`�k�r��l�H���͊��҂͍ŗD��ł�
�Ή����K�v�ł����A���ɂ������������a���ҁA���x�̍ЊQ�ŏ��Q��
�����芴���ǂȂǂň�Ë@�ւłً̋}�Ή���A����Ԃ����P�ł����
��Ɉڂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��P�[�X�͂�������o�Ă��邱�Ƃ͖ڂɌ�����
���܂��B
�@�����̂ł̔��f�����ł͌��E������܂��B���{�͋߂����ʗ��@������
���Ƃ̂��Ƃł����A���̂Ȃ��ł͂��Ђ����������������Ƃ��đΉ���
����悤�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł��B��Q�҂��a�A�����������҂ւ̑Ή�
�́A�������ē��ʂȂ��̂ł͂Ȃ���Ў҂��ׂĂ̐l�����̖��ł���A
�Ђ��Ă͔�Вn�ȊO�̍����S�̖̂��ł��B
�@�������͐k�БO����A��a���A���������̖�肪�A�����̓��ʂȐl
�����̖��ł͂Ȃ��A�N�������W���邩�킩��Ȃ����Ƃ��ĂƂ�
���邱�ƁA��a��A��Q�ґ���g�[���邱�Ƃ��A���{�̕����A���
�̐������グ���邱�Ƃł���A�������̊��҉^���A��Q�҉^���͂���
�����Љ�I�ȈӋ`�̂���^���ł���Ǝ咣���Ă��܂������A���̂��Ƃ�
���̐k�Б�̂Ȃ��ł���������ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���܂��B�i���J�j
���ȉ��A�X�ݏZ�̋v�ۓc��������̃��[�����Љ�܂��B�v�ۓc����
�͑S���S���a�̎q�ǂ���������ŁA�X���x���������Ă��܂��B
----------------
����A�X���̐�V���S��������ɁA��������Ў҂��ی�������
���A�Љ��E�J���e�����A�����i�q�ǂ��j�����p���Ă������Ȃ�
��ԂŎ�f�ł��邩�₢���킹���Ƃ���A���������̈�t�Ԃ̃l�b�g��
�[�N�ŁA�X�s�A�O�O�s�A���ˎs�Ōv�T�a�@������Ă�����͂�
������Ă���܂����B���ɁA�O�O�̈�t�͍O�O�ɔ��Ă����q�ǂ���
�S�������ɔC����ƌ����Ă���܂����B���J�Ȃ̒ʒB��ǂފԂ��Ȃ���
�t�B���Ǝ��œ����Ă���Ă��܂��B�i�ی��̌��͂R��11���Ɍ��J�Ȃ�
�ʒB���o�Ă��܂�������̈�t�͓ǂ�ł��鎞�Ԃ�����܂���j
���A���҂̂��߂̔�������A�����̂������Œ�������̐���
��������܂��B�܊p�������������~�����߂ɂ́A���n�ł̎��Ԕc��
�ƂƂ��ɑ���Ƃ�悤�A���{�ɋ����i�������ł��B���{�̓����͌��
���ɂȂ��Ă��܂��B���̏Z�ގO�����Вn�ł��B�Ôg�ʼn�œI�Ȕ�Q
�����n��A�`�ɂ̓{�����e�B�A�ƂƂ��ɕČR���{�����e�B�A�Ƃ���
��������ϋɓI�ɕ����Ɍ������x���������s���Ă��܂��B�i�l���A�����A
�d�@�A�R���j�B�ʂ����Đ��{�͔�Вn�Ɏ�����荞��ł���̂��H�^��
�Ɋ����Ă��܂��B
���T���j���ɎЗp�œ����֍s���܂����B�H�c��`�͔��Â��A�����Đl��
���Ȃ��d�Ԃ��l���܂�ŁA�ǂ��ɍs���Ă����̔߂������o���܂����B
���n�̕����ƂƂ��ɁA���{�̌o�ς����C�����߂���悤�A�܂��͓���
�����C�ɂȂ�Ȃ���Ɗ����܂����B
������A����A�����ŊJ�Â��Ċ��C�t���܂��傤�B
���i�o�`�́A�S���Q���`�R���̂Q���ԁA�����s���ŗ�������J�ÁB�܂�
�����_�ł́A�����\��ǂ���A�T���Q�X���i���j�ɑ�V��A���R�O
���i���j�ɍ����s�����s�����ƂƂ��A����O���̂Q�W���i�y�j�ɁA
��P�P������A������������ŊJ�Â��邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�y���R�אl�搶�i�S����a�Z���^�[�������j����̃��b�Z�[�W�Љ�z
���쌴����\���A�S����a�Z���^�[�������ŁA�������_�E�_�o�Z
���^�[�a�@���̎��R�搶����A���̂悤�ȃ��[��������܂����Ƃ̘A��
������܂����̂ŏЉ�܂��B
----- Original Message -----
�쌴�����l
��k�Ђƌ������̎��ɍ���ɊF���ʂ��Ă��܂��B
��a���҂���ւ̎x���A�l�X�s���Ă��܂����A�ł��[���ŋꂵ���Ή�
�Ɋ撣���Ă����́A���k��w�̐ؐ��u�搶�B�̊����Ɍ����܂��B
�{��̍���搶���̐l�H�ċz�ɂȂ��ꂽ���҂���B�̋~���ɓ��{�_�o
�w��⍑���a�@�@�\�̕a�@��搶������{�݂�h����Ðl�̃��X�g
���쐬���ē�a��Âɋ��͂��Ă��܂��B
��̋����Ɋւ��Ă͊e�w��������Ă�������܂��B
���R�אl�@�Ɨ��s���@�l�@�������_�E�_�o��Ì����Z���^�[�a�@��
�y�L������z
����ЎҎx�����J�ȁA�����N���ی����Ə�������
�i���{�o�ϐV��2011�N3��25���t�����j
�@�����J���Ȃ͓����{��k�ЂŔ�Ђ������Ǝ҂ƌٗp�҂ɂ��āA
�����N���ی�����Ə����錟���ɓ������B
�@�Ə��ɂ͖@�����ɂ������݂���K�v������B���Ȃ͐��{�S��
�Ŕ�ЎҎx���@���Ƃ�܂Ƃ߂鎞�ɁA����@�荞�ޕ��j�B�n�k
�Ŕ�Q�����l���Ƃ��x������̂��_�����B
�@���c�Ǝ҂�p�[�g�J���҂��������鍑���N���ł́A���łɔ�Ў�
�̕ی�����Ə����Ă���B����A��Ђœ����l����������N���͍�
�Q�ɂ��Ə����x��݂��Ă��Ȃ��B
�@�����P�X�X�T�N�̍�_��k�Ђ͔�Q���傫���������߁A��ЎҌ�
���ɕی����̖Ə����x��݂����B���J�Ȃ͓����{��k�Ђ��X�T�N��
��Q����Ɣ��f�A�Ăѓ����݂���K�v������Ƃ݂Ă���B
�@����̑Ώۂɂ͊��A�{��A�������ȂǂōЊQ�~���@���K�p����
���n���z��B�Ζ��悪��Ђ��Ď��Ƃ����藧�����A�x�����鋋�^
����������������ł����ƂƂ��̏]�ƈ����Ə��̑ΏۂɂȂ�B
�@�܂��A��_��k�Ђ̎��̓���ł́A�N���ی����̖Ə����Ԃ͕ی�
�����x���������̂Ƃ݂Ȃ��Ă����B��������l�̈����ɂ��邩�͍�
��l�߂�B
�@���łɌ��J�Ȃ͔�Вn�ɑ��A�����N���ی����̔[�t�������n��
�Ă���B�����N���Ƌ����ۂ̌��N�ی��ɂ��āA��Ђ�������
���̏ꍇ�A�ЊQ�ɂ�鍬�����I����Ă���ی����̔[�t�����߂�B
�@�ΏۂƂȂ�n��͐X�A���A�{��A�����A���̂T���B�Ώێ�
�Ǝ҂͂P�P���ɂȂ錩���݂��B�a����������̈������Ƃ������~��
���B
�@���c�Ǝ҂�p�[�g�œ����l�����鍑���N���ł́A�\���葱������
��Εی����i���P���T�P�O�O�~�j�̎x������Ə�����B�Z���ƍ�
�Ȃǂ������ނ˂Q���̂P�ȏ㎸�����l���ΏۂŁA�V�����܂łɑS��
�̔N���������Ŏ葱������K�v������B
-----------------------------------------------------------
����a���҂�f�@�A�w��a�@�ȊO���|��d�Ō��J�Ȓʒm
�i�����V��2011�N3��25���t�����j
�@�����J���Ȃ͂Q�S���A�����d�͂Ⓦ�k�d�͂ɂ��v���d������A
��a��l�H���͂̊��҂炪���ȕ��S����������Ă���w��̈�Ë@
�ւ���f�ł��Ȃ��ꍇ�����邱�Ƃ���A�ʂ̕a�@�ł���f�ł����
���ɂ���[�u��s���{���ɒʒm�����B
�@���J�Ȃɂ��ƁA���⎩���̂���Ô���������Ă����a���҂�
��U�W���l�B�ʏ�́u���莾����Îҏv���g���A�����ɋL��
���w���Ë@�ւŎ��Â��邪�A�v���d�ɂ��w���Ë@�ւ�
�@�\���Ȃ��ꍇ���N���蓾�邽�߁A�Љ��ȂǕʂ̕a�@�ł���f��
����悤�ɂ���B
�@�܂��A�l�H���͊��Җ�R�O���l�͏�Q�Ҏ蒠���擾���Ă���P�[
�X���������A�u�����x����Îҏv�ɋL�����w��̈�Ë@�ֈȊO
�ł���f�ł���悤�ɂ���B�y��q�b�z
���ʒm�́A�����J���ȃz�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j8f-img/2r985200000165ko.pdf
------------------------------------------------------------
���t�@�C�U�[�@�����̃I�����C���Ǘᑊ�k���J�n
�@���e��GIST
�@�i�~�N�XOnline�@2011/03/24 05:02�j
http://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/40500/Default.aspx
�@�t�@�C�U�[�͂Q��������A�����Ɋւ��Ĉ�t����I�����C��
�ŏǗᑊ�k���t������g�݂��n�߂��B
�@���Ђ̈�Ï]���Ҍ�������������E�F�u�T�C�g�uPfizerPRO�v��
�V�R���e���c�Ƃ��āuPfizerPRO CaseStudy�v���J�݁B���e�Ƃ�
�Ċ����GIST�i�����NJԎ���ᇁj��Ώۂɂ����uGIST�Ǘᑊ
�k���v�̃T�[�r�X���n�߂��B
�@�ʏǗ�̑��k����オ�A���ɗՏ��I�ɎQ�l�ɂȂ�Ǘ�
�ɂ��Ă̓f�[�^�x�[�X�o�^��PfizerPRO����ɑ��Č��J����B
�@���Ђ͂��̃r�W�l�X���f���ɂ��ē����o�肵�Ă���B
�@���Ђ͍���̐V�R���e���c�ɂ��āA�u�����ɑ��ēK��
�Ǘᑊ�k���ł���d�g�݂ƁA�X�Ƀf�[�^�x�[�X�����邱�ƂŁA��
���̈�ÊW�҂ŏ��̋��L�Ǝ��Â̍œK����}�邱�Ƃ�ړI��
���Ă���v�Ɛ������Ă���B
�@GIST�͔��ǐ���10���l������Q�l�Ɣ��Ɋ�Ȃ���B���Â̑I
�����͎�Ɏ�p�ŁA�Ö@�̓C�}�j�`�u�A�X�j�`�j�u�̂Q�܂Ɍ�
����B�����GIST�Ǘᑊ�k���͕a���A���ː��A���ȁA�O�Ȃ̊e
�����GIST���Â̐��Ƃ̋��͂Ă���A�b�s��w���摜�t�@
�C���Ȃǂ��܂߂ăI�����C���ŏǗᑊ�k�ł���B���k�@�\�͉����
�t����A���J�Ǘ�͉���S�����Q�Ɖ\�B
�@���Ђ́A��×p���i�̏��Ȃǂ��C���^�[�l�b�g������肷��
��Ï]���҂������Ă��邽�߁A�l�q�ɂ����ɂ��킹�ăl�b
�g�ł̏�����������K�v������Ɣ��f���APfizerPRO��10�N
�Q������J�n�����B
�@�ŋ߂ł�The New England Journal of Medicine�iNEJM�j�Ɍf��
����Ă���S�Ă̘_�����t���y�[�p�[�ʼn{���ł���悤�ɂ���ȂǁA
�R���e���c������������B
�y���Ғc�̂���̘A���E���z
���S���S���a�̎q�ǂ�������----------------------------------
�i�����ǒʐM�u�n�b�g�͂��Ɓv�Վ���2011�N3��24���t���j
�� ��Вn�̎x�����
����茧�x�����@����݂Ȃ����ł��I
�x�����̋e�r����̉�����A���b���܂����B
�����R�l�Ŏ蕪�����ĉ���̈��ۊm�F�̘A�������܂����B�C������
�Z��ł�������Ôg�̉e���Ŕ�Q���Ђǂ������ł����A���ۂ͊m�F��
���������ł��B�����ł��A�K�\�����Ɠ����A�H�i�A�����Ȃ���Ԃ��[
���ł��B�u�݂Ȃ���̐����ƂĂ��������v
������畷�����Ă����b�c
����������i��D�n�s�j�A����͖��������������X�͒Ôg�̉e���Ń_��
�ɂȂ��Ă��܂����B
����D�n�s�̒��w�P�N���̉���̕��́A���܂��ܕa�@�ɍs���Ă��Ċw
�Z���x��ł������A�����w�Z�̓������͍s�����킩��Ȃ���������B
�Ȃ��Ȃ��Ă��܂������a�@�܂ōs�����ɂ����B�Ȃ�Ƃ��ً}�ԗ�
�ɏ悹�Ă�����ĕa�@�ɍs�����Ƃ��ł����B���̌�͐e�ʂ̉Ƃɔ��
������B
���e�r����̂��q��������[�t�@����������ł��Ď��]�Ԃɏ��̂�
��߂�悤�Ɍ����Ă��āA�ӂ���w�Z�܂�30�������ĕ�����
�ʂ��Ă���B���x�������g�Q���Ƃ��Ă���g�̂ŁA�����̕��˔\
���S�z�����A����}��������ɂ��K�\�������Ȃ��Ăł��Ȃ��B
�������z���ÃZ���^�[�ɐS���a�̊��҂͏W�����Ă���B���
�ƕa�@�ɍs���Ă��Q�T�ԕ��������炦�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
���ݑ�_�f�̐l�A�_�f���c��킸���ɂȂ�q���q���������A�Ȃ�Ƃ�
��ЂɘA�����Ƃ�ď��������B
���w�Z�ɂ��Ēn�k�����āA�Z��ɃW�����p�[�����Ŕ������A�e��
�̘A�����Ȃ���Ȃ��Ăނ����ɂ��Ă��炦�Ȃ��āA���ׂ��Ђ��Ěb
�����Ђǂ��Ȃ��Ă��܂��̒�����邭�Ȃ����B
28���ɂ͖�������J���āA���ꂼ�ꕷ�����������̕��̏�����
�����\��ł��܂��B
���X���x����
��Вn����X���̈�Ë@�ւɂ�����ꍇ�ɂ��Ă̏��
�i�v�ۓc�x��������̃��[���Ɠd�b�j
�X���O����̔��҂ŐS���a���̐f�ÂȂǎ����Ή��ɂ��m�F��
�܂����B
�₢���킹������
�����A�{��A��肩��̔��҂����X�����Ɉړ����n�߂Ă��܂����A
�{���ɔ����S���a���E�҂̐f�@�A���Âɂ������Ď��̎������O��
�Ă���܂��B
�@ ���N�ی��������Ă��Ȃ��i���o�A�����ē������Ȃ������j
�A �Љ�Ȃ�
�B ��p���p���Ă������Ȃ��B
���̂悤�ȃP�[�X�ʼnʂ����Ď�f�ł���̂��H�@����Ă����a
�@�͂��邩�H
�����a�@�@�\�O�O�a�@�����H�搶�֊m�F���������ʁA���L�̈�Ë@��
�őΉ����Ă�������Ƃ̉����������܂����B
�E�X�s���X�s���a�@�i�����ȁE�s���搶�j
�E�O�O�s���O�O��w��w���t���a�@�i�����ȁE�����搶�j�A�����a�@
�@�@�\�O�O�a�@�i�����ȁE�����搶�j
�E���ˎs���X�J�Еa�@�i�����ȁ@����搶�j�A���ˎs���a�@
��t�A�a�@�Ԃ̌��ȂǍ����搶���S�ʓI�Ƀo�b�N����Ƃ������Ƃ�
�����B
�������J���ȁ@�ی��Lj�Éۂ�3/11�����A���u��ی��ҏؓ��̒�
�ɂ��āv�ɂ����āA�u�����A���N�����A��p�ҕی��̔�ی��҂ɂ�
���Ă͎��Ə����A�������N�ی��y�ь������҈�Ð��x�̔�ی��҂�
�����Ă͏Z����\�����Ă邱�Ƃɂ��A��f�ł���戵���Ƃ���̂�
���̎��{�y�ъW�҂ɑ�����m�ɂ��āA��R�Ȃ��������ꂽ���B�v
�Ƃ����w�����o�Ă��܂��B�������A���[�̈�Ë@�ւ܂ŁA���������A
�����͂����Ĕ�Вn�܂ōs���͂��Ă��Ȃ��悤�ŁA����́A���
�x�����n���̈�t�ɓ������������Đ搶�������Ă��������܂����B��
���A�A��B�ɂ��ẮA�����J���Ȃ���͉��̎w�����o�Ă��炸�A��
�������Ë@�֔C���ł��B�����J���Ȃ���́u�k�Б�v�Ƃ��Ă���
����̘A���������o���Ă��܂����A���ꂾ���ł͕s�\���ŁA����̂�
���ɒn���̈�t�̂��s�͂ɂ��Ή��ł��Ă���̂�����̂悤�ł��B
�i�{�������ǁj
���������x�����i�Ζ؎x�������獡�䗝�����d�b�ŕ������j
�i22���i�j��10:30���A�����x�����̖Ζ���d�b�Ŕ�Џ�
�Ȃǂ��܂����j
�����̉Ƃ͕����w�ɋ߂��A�w���瓹�H�ɑ傫�ȋT�����Ă��܂��B
�S�����ƕ��݂̂����A�����̂Ƃ���͈�ԉw���牓���̂ł����A
�߂��Ƃ���A�Ԏ��A���F�A���F�ƂȂ��Ă���A�䂪�Ƃ��S��͖Ƃ��
�������A�X���Ă���Ƃ��������A�����A�s���猚���̎g�p�Ɋւ���
�f�f���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B��������A���ɂ��܂������A
��͎���ɖ߂�܂����B���i�a���j�͎����̖��̂Ƃ���ɂЂƂ܂��A
�����Ă��܂����A�X�g���X�������Ă���悤�ŁA��������ɖ߂�
��ɂȂ�Ǝv���Ă��܂��B
��N�A�����ő�����J�Â��鎞�ɁA������@��ɑS���̉���݂̂Ȃ�
��ɁA����A�����̏ꏊ���o���Ă��炨���ˁA�Ƙb���Ă����̂ɁA��
�����A����Ȍ`�ŕ����̖��O���S���ɍL����Ƃ͎v���܂���ł����B
�n�k�����邱�ƂȂ���A���A�����ň�Ԗ��ɂȂ��Ă���̂́A����
�ł��B��������Ă��Ȃ��n��ɂ��A���R�����͏Z��ł���A���
�v�ƌ�����炵�Ă���̂ɁA���]�ɂ��A�������Ă��錻��
�߂����ł��B�������͖����A�����ŕ�炵�Ă��܂��A���ː��ʂ����
�ɂȂ�قǂł͂Ȃ��̂ɁA�������畨���̗A�����x���ǂ�قǂ̔��
�����Ƃ����̂ł��傤���B��ÂɑΉ����Ăق����ł��B
���͎���ɂ�����̂�H�ׂĐ������Ă��܂��B�ߏ��̉������ƐH��
����������āA�[�H�����ɂ��Ă��܂��B�������o�Ă���悤�ɂȂ�A
�����A�ق��Ƃ��邱�Ƃ�����܂��B
�������A�������b�Ƃ��āA
����Q�Ҍٗp�ō̗p����A�k�Г��ً̋}���ɂ͂��Ԃ��ē����Ă����
�͂��������̂ɁA�݂�Ȃ����肾���A�����������ē��������r���ő�
�͂��������A���铯���Ƃ͗���Ă��܂����B
�����ł́A���ׂ��͂��͂��߂Ă��āA�a���Ɋ���������̂���
�킭�ĕt���Y���Ă���Ɓu�ߕی�v���ƌ���ꂽ�B
���e���r�ł́A���Ȃ�������C�ɗV��ł���q�ǂ��A�ϋɓI�Ɏ�
�`�����Z���Ȃǂ��ʂ��o����Ă��邯��ǁA�����Ƃ��ē����Ȃ��q��
��������B���N�����Q�҂ɔz�����ƌĂт����Ă��Ă��A���̂Ȃ�
�ɂ͓�����Q�҂͊܂܂�Ă��Ȃ��B���������a�C�̎q�ǂ��̂��Ƃ͓�
�ɂȂ��B���Ԃɕa�C�̂��Ƃ��F�m����Ă��Ȃ��ȂƊ�����B
�������������҂��������Ƃ��炦�Ă��A���܂łP���������炦����
���A���̖�̔z�����u���ɂȂ邩�킩��Ȃ��v�ƂQ�T�ԕ���������
���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ̂ł����܂ň����Ȃ��l���A���炦�邤����
�Ɛf�@���A���������Ă��邱�Ƃ�����B�x���̐l�Ƙb��������
����Ȏ��ԂɂȂ�����A�a�C�̎q�������ĂȂ�Ă����Ȃ���ˁB�ߍ�
�ȏɑς���Ȃ���B���N�Ȑl�ł��h���̂ɁB
------------------------------------------------------------
���e���a�c�̂̎��g�݂�����A�i�o�`�����ǂɂ����肭�������B
*------------------------------------------------------------*
���ً}�ȏꍇ�̘A���͐��J�̌g�сi090-8501-4281�j�܂ł��肢���܂��B
�Ȃ��A���[���͐����`�F�b�N���Ă��܂��B
�i�o�`�z�[���y�[�W�@http://www.nanbyo.jp/
�k�Џ��u���O�y�[�W�@http://blog.goo.ne.jp/jpa2011
�i������ɐ��������������j
���{��a�E���a�c�̋��c����ǒ��@���J�K�i
���̂i�o�`�iJapan Patients Association�j
��162-0822�����s�V�h�扺�{�䒬2-28
�ѓc���n�C�^�E��610��
�d�b03-6280-7734�@�e�`�w03-6280-7735
http://www.nanbyo.jp/�@jpa@ia2.itkeeper.ne.jp
*------------------------------------------------------------*
JPA�k�Џ��i��13��j
2011.03.25
�y�x�����z
�����t�{�ɔ�ЎҐ����x�����ʑ��{�������ǂ�ݒu�i�R���Q�O���j
�@���{�ً̋}�ЊQ���{���́A�R���Q�O�������t�{�u���ɁA��Ў�
�����x�����ʑ��{�������ǂ�ݒu�����Ɣ��\���܂����B
�@�����ǁ@��\�d�b03-3581-4571�i���ʁj FAX 03-3581-6282�`4
�@���[���A�h���X f_bousai001@net.bousai.go.jp
�y�L������z
���u��Ô�ȕ��S�u�P�\�łȂ��Ə����v- �k�Ў���v
�i 2011�N03��23�� 21:06 �L�����A�u���C�� �j
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/33215.html
�@���{��t���3��23���̋L�҉�ŁA�n�k�̔�Q�ŕی��f�ÂȂǂ�
���ȕ��S���̎x�����������Ў҂ɂ��Ă͓��ʁA�x������Ə���
�ׂ��Ƃ̍l�����������B
�@����́A�����J���Ȃ�15���ȍ~�ɏo���������A���������́B
�@���Ȃ́A���k�n�������m���n�k��A���̌�̒��쌧�k���̒n�k�ɂ�
���ďZ�����S��Ȃǂ��Ď��ȕ��S���̎x�����������Ў҂ɂ�
���āA���ʁA�x������5�����܂ŗP�\����悤�s���{���ȂǂɎ����A
�����Ă���B�Ώێ҂̗v���́A���Z���̑S����A�S���ā���Ȑ��v��
���҂̎��S�A�s���s���\�Ȃǂ̂����ꂩ��\�����Ă邱�ƁB
�@�������������A���ɂ��ė�ؖM�F��C�����́A�u���̑Ή��ł͕s
�\���v�Ǝw�E���A�u�P�\�v�ł͂Ȃ��u�Ə��v�őΉ����ׂ��Ƌ��������B
���̂ق��A���s���s�����������v�ێ��҂̍s�������炩�ɂȂ����ꍇ
�ł��A���ʂ͎��ȕ��S����Ə����遤��Вn�̕��������Ȃ���A
���Ԃ���������\���Ƃ��K�v�Ƃ̍l�����������B
�@����A��Ў҂����ꂽ��Ë@�ւ̓��@���Ґ�����Ö@��̋���
�a�����߂��Ă��A���@��{���͌��Z����Ȃ��ȂǂƂ���15���t��
�����A���ɂ��ẮA����Вn������@���҂����ꂽ�ꍇ�A����
���@�̎�舵���ɂ��ׂ������ꊳ�҂�90��������@�ɂ���
���@��{������������Ȃ��悤�z�����ׂ��\�Ƃ����B
�@��؏�C�����ɂ��ƁA�����̎咣�ɂ��Ă͊��ɁA���J�Ȃɗv
�����Ă���Ƃ����B
���@���̌��ɂ��ẮA�S���ی���c�̘A����i�ےc�A�j��3��17��
�ɗv�]�����o���Ă��܂��B�i���j
http://hodanren.doc-net.or.jp/news/unndou-news/110317futan.pdf
�����t�{�ɔ�ЎҐ����x�����ʑ��{�������ǂ�ݒu�i�R���Q�O���j
�@���{�ً̋}�ЊQ���{���́A�R���Q�O�������t�{�u���ɁA��Ў�
�����x�����ʑ��{�������ǂ�ݒu�����Ɣ��\���܂����B
�@�����ǁ@��\�d�b03-3581-4571�i���ʁj FAX 03-3581-6282�`4
�@���[���A�h���X f_bousai001@net.bousai.go.jp
�y�L������z
���u��Ô�ȕ��S�u�P�\�łȂ��Ə����v- �k�Ў���v
�i 2011�N03��23�� 21:06 �L�����A�u���C�� �j
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/33215.html
�@���{��t���3��23���̋L�҉�ŁA�n�k�̔�Q�ŕی��f�ÂȂǂ�
���ȕ��S���̎x�����������Ў҂ɂ��Ă͓��ʁA�x������Ə���
�ׂ��Ƃ̍l�����������B
�@����́A�����J���Ȃ�15���ȍ~�ɏo���������A���������́B
�@���Ȃ́A���k�n�������m���n�k��A���̌�̒��쌧�k���̒n�k�ɂ�
���ďZ�����S��Ȃǂ��Ď��ȕ��S���̎x�����������Ў҂ɂ�
���āA���ʁA�x������5�����܂ŗP�\����悤�s���{���ȂǂɎ����A
�����Ă���B�Ώێ҂̗v���́A���Z���̑S����A�S���ā���Ȑ��v��
���҂̎��S�A�s���s���\�Ȃǂ̂����ꂩ��\�����Ă邱�ƁB
�@�������������A���ɂ��ė�ؖM�F��C�����́A�u���̑Ή��ł͕s
�\���v�Ǝw�E���A�u�P�\�v�ł͂Ȃ��u�Ə��v�őΉ����ׂ��Ƌ��������B
���̂ق��A���s���s�����������v�ێ��҂̍s�������炩�ɂȂ����ꍇ
�ł��A���ʂ͎��ȕ��S����Ə����遤��Вn�̕��������Ȃ���A
���Ԃ���������\���Ƃ��K�v�Ƃ̍l�����������B
�@����A��Ў҂����ꂽ��Ë@�ւ̓��@���Ґ�����Ö@��̋���
�a�����߂��Ă��A���@��{���͌��Z����Ȃ��ȂǂƂ���15���t��
�����A���ɂ��ẮA����Вn������@���҂����ꂽ�ꍇ�A����
���@�̎�舵���ɂ��ׂ������ꊳ�҂�90��������@�ɂ���
���@��{������������Ȃ��悤�z�����ׂ��\�Ƃ����B
�@��؏�C�����ɂ��ƁA�����̎咣�ɂ��Ă͊��ɁA���J�Ȃɗv
�����Ă���Ƃ����B
���@���̌��ɂ��ẮA�S���ی���c�̘A����i�ےc�A�j��3��17��
�ɗv�]�����o���Ă��܂��B�i���j
http://hodanren.doc-net.or.jp/news/unndou-news/110317futan.pdf
���̌�̓��k�x������̈��ۂɂ���
2011.03.24
�݂Ȃ���
�������̂ɂ��s�����܂��܂������Ă���܂����A�����ɂ��������ł��傤���B
�k�В��ォ��A�ł��������̈��ۊm�F������Ă܂���܂�����
�X�A�H�c�A�R�`�A�{��A�����̊e�O���[�v�̕��X�̂قڑS���̖������m�F�������܂����B
�݂Ȃ��܂̂��Z�܂��̂Ƃ���ł��A���낢���ςȂ��Ƃł��傤��
�͂����킹�Ă��̓�ǂ������Ă����܂��傤�B
�|�̎q�̉�@�����ꓯ
�������̂ɂ��s�����܂��܂������Ă���܂����A�����ɂ��������ł��傤���B
�k�В��ォ��A�ł��������̈��ۊm�F������Ă܂���܂�����
�X�A�H�c�A�R�`�A�{��A�����̊e�O���[�v�̕��X�̂قڑS���̖������m�F�������܂����B
�݂Ȃ��܂̂��Z�܂��̂Ƃ���ł��A���낢���ςȂ��Ƃł��傤��
�͂����킹�Ă��̓�ǂ������Ă����܂��傤�B
�|�̎q�̉�@�����ꓯ
�i�o�`����@�u���k�֓���k�ЁF��a�̎q�ǂ��x���_�ސ�l�b�g���[�N�v���ł��܂���
2011.03.23
��a�l�b�g���̂��m�点�ł��B
���̂��т̑�n�k�E�Ôg�̔�Q�ɑ���ꂽ���X�ɂ́A�������肨�������\���グ�܂��B
�������_�ސ쌧�����Ȋw��n����̏����Ȉ�́A���̓�ǂɗ������������k�E�֓��̏����Ȉ�݂̂Ȃ��܁A�q�ǂ������Ƃ��̌�Ƒ��ɁA���ꂼ��̗��ꂩ�班���ł�����`���ł���ƍl���Ă���܂��B
�������́A�k�Ќ�ɓ�a�̎q�ǂ����������Â̒��f��A��܂̌͊��ɂ��a�C�̍ĔR�ɍ������Ă���Ƃ̏��ɐڂ��܂����B�܂��A�K�\�����̂Ȃ����A2���A3��������ʼn��l�ɂ��ǂ蒅���A����Ɩ�܂̓�����a�C�����������ނ��Ƃ��ł�������o�����܂����B�����ŁA�_�ސ쌧�����Ȋw��n����ł͐_�ސ쌧���̍�����Ë@�ւ��l�b�g���[�N�Ōq���A��a�̎q�ǂ�����������Ď��Â��p���ł���̐��𐮂��܂����B
�����ɂ����������̂́A����ł��B����A����ɑ����̈�Ë@�ւ������̏�W�܂邱�ƂɂȂ��Ă���A����A��O��Ƃ��Ă������ł���Ǝv���܂��B
�܂����X�g�������ɂȂ�A�q�ǂ�����̕a�C�ɑΉ��\�Ǝv�����Ë@�ցi�S����j�ɘA�����Ƃ��Ă݂ĉ������B���邢�́A�厡��̐搶�Ƒ��k�Ȃ����Đ搶����S����֘A�����Ƃ��đՂ���K���ł��B
�悤�₭18���ȍ~�A�����{���Ζ��ƃK�\��������Вn�ɉ^�т��܂��Ƃ̏����܂��B���������āA�_�ސ�܂ł̃A�N�Z�X�͎ԁA�o�X�Ȃǂ��l�����܂��B����A���q���A���̑��̋@�ւɃw���R�v�^�[��v���Ղ��Ă����\�ł��B�_�ސ쌧���̒����n�̃w���|�[�g�͎g�p�\�ȏ�Ԃɂ���܂��i���l�s����w�����a�@�i���Y�j�̗��ɂ���w���|�[�g�A�s��������ÃZ���^�[����̃w���|�[�g�Ȃǁj�B
��a�̎q�ǂ��������A���̓�ǂɂ����Ă����Â��p���ł���悤�A�s���̕��X�A�֘A�@�ւ̕��X�ɂ͊i�i�̂��z����ɂ��肢���鎟��ł��B�ǂ����X�������肢�\���グ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011�N3��18��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ސ쌧�����Ȋw��n����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@��@���u
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���k�֓���k�Ћً}�x���`�[��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���A�Ό��@�~�A�X�@�뗺
���̂��т̑�n�k�E�Ôg�̔�Q�ɑ���ꂽ���X�ɂ́A�������肨�������\���グ�܂��B
�������_�ސ쌧�����Ȋw��n����̏����Ȉ�́A���̓�ǂɗ������������k�E�֓��̏����Ȉ�݂̂Ȃ��܁A�q�ǂ������Ƃ��̌�Ƒ��ɁA���ꂼ��̗��ꂩ�班���ł�����`���ł���ƍl���Ă���܂��B
�������́A�k�Ќ�ɓ�a�̎q�ǂ����������Â̒��f��A��܂̌͊��ɂ��a�C�̍ĔR�ɍ������Ă���Ƃ̏��ɐڂ��܂����B�܂��A�K�\�����̂Ȃ����A2���A3��������ʼn��l�ɂ��ǂ蒅���A����Ɩ�܂̓�����a�C�����������ނ��Ƃ��ł�������o�����܂����B�����ŁA�_�ސ쌧�����Ȋw��n����ł͐_�ސ쌧���̍�����Ë@�ւ��l�b�g���[�N�Ōq���A��a�̎q�ǂ�����������Ď��Â��p���ł���̐��𐮂��܂����B
�����ɂ����������̂́A����ł��B����A����ɑ����̈�Ë@�ւ������̏�W�܂邱�ƂɂȂ��Ă���A����A��O��Ƃ��Ă������ł���Ǝv���܂��B
�܂����X�g�������ɂȂ�A�q�ǂ�����̕a�C�ɑΉ��\�Ǝv�����Ë@�ցi�S����j�ɘA�����Ƃ��Ă݂ĉ������B���邢�́A�厡��̐搶�Ƒ��k�Ȃ����Đ搶����S����֘A�����Ƃ��đՂ���K���ł��B
�悤�₭18���ȍ~�A�����{���Ζ��ƃK�\��������Вn�ɉ^�т��܂��Ƃ̏����܂��B���������āA�_�ސ�܂ł̃A�N�Z�X�͎ԁA�o�X�Ȃǂ��l�����܂��B����A���q���A���̑��̋@�ւɃw���R�v�^�[��v���Ղ��Ă����\�ł��B�_�ސ쌧���̒����n�̃w���|�[�g�͎g�p�\�ȏ�Ԃɂ���܂��i���l�s����w�����a�@�i���Y�j�̗��ɂ���w���|�[�g�A�s��������ÃZ���^�[����̃w���|�[�g�Ȃǁj�B
��a�̎q�ǂ��������A���̓�ǂɂ����Ă����Â��p���ł���悤�A�s���̕��X�A�֘A�@�ւ̕��X�ɂ͊i�i�̂��z����ɂ��肢���鎟��ł��B�ǂ����X�������肢�\���グ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011�N3��18��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ސ쌧�����Ȋw��n����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@��@���u
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���k�֓���k�Ћً}�x���`�[��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���A�Ό��@�~�A�X�@�뗺
�i�o�`����@�����{��n�k�y�`�����E����E��t�ł���T�C�g�܂Ƃ߁z
2011.03.23
���̂��т̑�k�Ђ͖��\�L�̍ЊQ�ƂȂ�܂����B
���̌㎟�X�Ƃ��낢��ȏ���Ă��܂��B
��Вn�ȊO�ŕ�炵�Ă��鎄�����ɂ͍��͂ł��邱�Ƃ������܂��B
�E����߁E�������߂��Ȃ�
�E�f�}���[�����܂킳�Ȃ��B
�E�ߓd�ɓw�߂�
�E�`�����ɂł���͈͂ŋ��͂���
�E����Ƀ{�����e�B�A�Ƃ��Ĕ�Вn�ɓ���Ȃ�
�Ȃǂł��ˁB
�`��������������m���߂Ă��Ȃ��ƁA�s���ȃT�C�g���o�Ă��Ă���̂Œ��ӂ��Ă��������B
�ȉ��́A�i�o�`��肨�m�点�̂��낢�날��`�����̃T�C�g�̂܂Ƃ߂ł��B
http://matome.naver.jp/odai/2129989217646489401
���̌㎟�X�Ƃ��낢��ȏ���Ă��܂��B
��Вn�ȊO�ŕ�炵�Ă��鎄�����ɂ͍��͂ł��邱�Ƃ������܂��B
�E����߁E�������߂��Ȃ�
�E�f�}���[�����܂킳�Ȃ��B
�E�ߓd�ɓw�߂�
�E�`�����ɂł���͈͂ŋ��͂���
�E����Ƀ{�����e�B�A�Ƃ��Ĕ�Вn�ɓ���Ȃ�
�Ȃǂł��ˁB
�`��������������m���߂Ă��Ȃ��ƁA�s���ȃT�C�g���o�Ă��Ă���̂Œ��ӂ��Ă��������B
�ȉ��́A�i�o�`��肨�m�点�̂��낢�날��`�����̃T�C�g�̂܂Ƃ߂ł��B
http://matome.naver.jp/odai/2129989217646489401
�l��PWS�e�q�̏W���̂��m�点
2011.03.22
���Q��w����w�����ʎx����w�@�����G�v�搶�����ɂ��W����
�U���P�Q���i���j���R�s��O����Z���^�[�ňȉ��̓����ŊJ�Â���܂��B
�X�F�O�O�@��t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���C��
�X�F�R�O�@�W���A���ȏЉ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@���̌�A���C�͌��C���A�^���ƗV�т͑̈�ف@�@�@�@�̈��
�P�O�F�O�O�@�u���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�������j
�����F���R�s���a�@�����ȁ@�d�����q�搶
�u�̏d�̌��ʂɐ����������l��PWS�̂P��v
�u�t�F�Z�F�ʎq�a�@�����ȁ@���쏺�搶
�����F���Q��w��w���Ō�w�ȁ@�����c�q�搶
�uPWS�ɂ����鐬�l�a�i���ɓ��A�a�j�ɑ�����g�݁v
�u�t�F���݂̂��a�@�����ȁ@���c���搶
�P�P�F�O�O�@�u��
�����F���Q��w����w�����ʎx����w�@�����G�v�搶
�uPWS�̍ŋ߂̘b��v�@
�u�t�F�Ջ���ȑ�w�z�J�a�@�����ȁ@�i��q�Y�搶
�P�Q�F�O�O�`�P�R�F�O�O�@���H�F���O�܂��͌��C���@�@
�P�R�F�O�O�@�u��
�����F���Q�����q�ǂ��È�Z���^�[�����ȁ@��{�T�V�搶
�uPWS�Ƒ��^�v�@
�u�t�F�Ջ���ȑ�w�z�J�a�@�����ȁ@����M�s�搶
�P�R�F�R�O�@�𗬉�
�u�t�����͂�ł̍��k��
�P�T�F�O�O�@���U
���Q���
�u�P���Q���R�[�X�v
�h����A�H��A�����㓙
��l�@��l�F4�C500�~
�@�@�@�q�ǂ��F4�C000�~
�u�P���@���A��R�[�X�v
�����A�����㓙
��l�@��l�F500�~
�@�@�@�q�ǂ��F500�~
�\����܂��A�{�����e�B�A����A�W�҂��������z�ƂȂ�܂��B
�Ȃ��A�Q����̎x�����͓�����t�̏�ł��肢���܂��B
���\�����݂̓_�E�����[�h���L���̏�T���Q�T���܂łɃ��[����FAX�Œ����搶�܂ł��\�����݂��������B
�U���P�Q���i���j���R�s��O����Z���^�[�ňȉ��̓����ŊJ�Â���܂��B
�X�F�O�O�@��t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���C��
�X�F�R�O�@�W���A���ȏЉ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@���̌�A���C�͌��C���A�^���ƗV�т͑̈�ف@�@�@�@�̈��
�P�O�F�O�O�@�u���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�������j
�����F���R�s���a�@�����ȁ@�d�����q�搶
�u�̏d�̌��ʂɐ����������l��PWS�̂P��v
�u�t�F�Z�F�ʎq�a�@�����ȁ@���쏺�搶
�����F���Q��w��w���Ō�w�ȁ@�����c�q�搶
�uPWS�ɂ����鐬�l�a�i���ɓ��A�a�j�ɑ�����g�݁v
�u�t�F���݂̂��a�@�����ȁ@���c���搶
�P�P�F�O�O�@�u��
�����F���Q��w����w�����ʎx����w�@�����G�v�搶
�uPWS�̍ŋ߂̘b��v�@
�u�t�F�Ջ���ȑ�w�z�J�a�@�����ȁ@�i��q�Y�搶
�P�Q�F�O�O�`�P�R�F�O�O�@���H�F���O�܂��͌��C���@�@
�P�R�F�O�O�@�u��
�����F���Q�����q�ǂ��È�Z���^�[�����ȁ@��{�T�V�搶
�uPWS�Ƒ��^�v�@
�u�t�F�Ջ���ȑ�w�z�J�a�@�����ȁ@����M�s�搶
�P�R�F�R�O�@�𗬉�
�u�t�����͂�ł̍��k��
�P�T�F�O�O�@���U
���Q���
�u�P���Q���R�[�X�v
�h����A�H��A�����㓙
��l�@��l�F4�C500�~
�@�@�@�q�ǂ��F4�C000�~
�u�P���@���A��R�[�X�v
�����A�����㓙
��l�@��l�F500�~
�@�@�@�q�ǂ��F500�~
�\����܂��A�{�����e�B�A����A�W�҂��������z�ƂȂ�܂��B
�Ȃ��A�Q����̎x�����͓�����t�̏�ł��肢���܂��B
���\�����݂̓_�E�����[�h���L���̏�T���Q�T���܂łɃ��[����FAX�Œ����搶�܂ł��\�����݂��������B